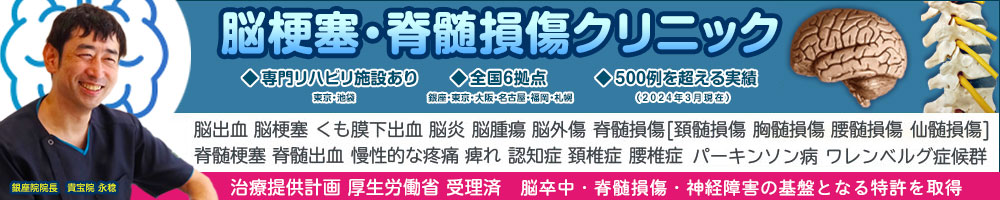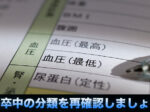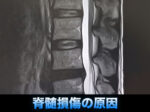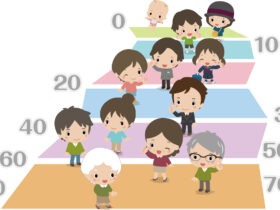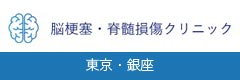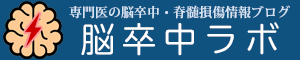《 目 次 》
私たち昭和の年代のアイドルであった西城秀樹さんが62歳の若さで急逝されました。
その死因は急性心不全と云うことです。
2度にわたる脳卒中を起こされていることを考えると、その背景には長年の高血圧があったのでしょう。
男性平均寿命が80歳を超す今の時代、あまりにも早いお別れに、遺されたご家族のことを思うと、ご本人もさぞ心残りだったことでしょう。
もし、あなたがその立場だったらと考えたら…
ここでは改めて、脳卒中にならないよう、普段からの予防を考えてみましょう!
高血圧はなぜ怖い
血圧って何でしょう
病院や家庭で一度くらいは血圧を測った経験はあると思いますが、あまり血圧を測らない方にとって、血圧計に表示される「上の血圧が130、下の血圧が85」と云う数値を見てもなにかピンと来ない方が多いようです。
ですからまずは、「血圧」について、お話しましょう。
「血圧」とは心臓から送り出される血液が、血管の内壁を押す力(圧力)のことです。
例えば、ホースに水道の水を多量に流して、張り詰めた状態にすると、ホースには高水圧がかかっています。
また、ホースを押さえて水の流れを悪くすると、少ない水量でもそこから後ろの部分は張り詰めた状態になります。
これと同じことで、心臓が送り出す血液量(心拍出量)と、それを流す血管の通りづらさ(末梢血管の抵抗)などの要因で、血圧も決まります。
私たちは自分のホースを出来るだけ傷めない様に気を付けて一生使い続けなければいけません。
そうです、一生です。私たちの体は一生乗り続けなければいけない車と一緒です。
出来るだけ大事に乗り続けるには、そのための知識とメンテナンスが必要になります。
最大血圧(収縮期血圧)
心臓が収縮して全身に血液を送り出す時、血管に加わる圧力は最大になり、この時の圧力を最大血圧と云います。
最小血圧(拡張期血圧)
心臓が拡張して全身に送り出した血液が心臓に戻る時に、血管への圧力は最小になり、この時の圧力を最小血圧と云います。
あなたの血圧は正常?
成人の血圧分類
収縮期血圧と拡張期血圧が異なる分類の場合は、高い方に分類に入れます。単位:㎜Hg
| 分類 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 |
|---|---|---|
| 正常域血圧 | 至適血圧 | 120未満かつ80未満 |
| 正常血圧 | 120~129かつ | または80~84 |
| 正常高値血圧 | 130~139かつ | または85~89 |
| 高血圧/Ⅰ度高血圧 | 140~159かつ | または90~99 |
| Ⅱ度高血圧 | 160~179かつ | または100~109 |
| Ⅲ度高血圧 | 180以上かつ | または110以上 |
| (孤立性)収縮期高血圧 | 140以上かつ | 90未満 |
※至適血圧とは血圧正常値の範囲において、最も数値の低い項目で「極めて適している」、「理想的」とされる血圧の数値を云います。

高血圧の症状
高血圧による頭痛
ストレスなどによる頭痛と高血圧による頭痛では、そのメカニズムが異なります。
一般的な頭痛は何らかの要因で脳の血管が拡張して、神経を刺激することで起こるとされていますが、高血圧による頭痛では脳の拡張はありません。
拡張されないのに頭痛が起こるのは脳内で動脈硬化などの、何らかの異変が生じているためです。
他の理由による頭痛と見分けるのは難しいですが、頭痛も高血圧の症状の1つであることは覚えておいてください。
高血圧による耳鳴り
高血圧の治療に使われる降圧剤が効きすぎた場合に現れることもありますが、血液の流れに異常がある場合に、首の頸動脈などの耳の近くを通る際に、「トクトク」や「ザーザー」と云った血管性耳鳴りが生じる場合が多いです。
高血圧によるめまい
一般的に、めまいは血圧が低い時に起こるので、高血圧によるめまいは、降圧薬を飲むことで血圧が下がって、起立性低血圧になり易くなります。
これは脳に循環する血液が一時的に足りなくなって、立ち眩みを起こして、めまいと感じるものです。
高血圧緊急症になると、めまいを起こして、脳や心臓、血管などに脳卒中や心不全などの問題を起こします。
高血圧による肩こり・腰痛
肩こり・腰痛の原因は、肥満、姿勢の悪さ、冷え性、眼精疲労、ストレスなどがあります。
高血圧には主に2つに分類され、原因が特定できない「本態性高血圧」と、血管疾患や内分泌疾患などの原因となる病気を伴う「二次性高血圧」です。
本態性高血圧には、ほとんど自覚症状がありませんが、臓器障害を伴うような重症の高血圧の場合は、頭痛、耳鳴り、めまい、肩こりなどの症状が現れることもあります。
高血圧による鼻血
鼻血には、「単純鼻出血」と「動脈性出血」があり、鼻出血の8割はキーゼルバッハと云う鼻の入り口付近の粘膜を傷つけることで起こる単純鼻出血です。
動脈性出血は、動脈硬化症、白血病、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)など、何らかの疾患によっておこる鼻出血を云います。
動脈性出血は、鼻からだけでなく歯茎から出血したり、時には脳出血を起こすこともあり、出血が激しく、なかなか止まらないのが特徴です。
高血圧症による鼻血は、鼻腔の後ろの太い血管壁などが動脈硬化によって傷むのが原因で、出血量が多く、口から溢れるほど激しく出血することもあるので、15分以上止まらない場合は病院へ行く必要があります。

高血圧から起こりやすい病気はこれ!
血圧が高いと血管(動脈)の壁により大きな圧力がかかり、血管(動脈)が傷みやすくなったり、動脈硬化のせいで、いろんな生活習慣病が起こりやすくなります。
脳血管障害:頭蓋内外の血管病変によって生じる脳神経系障害・脳機能障害の総称
- 脳出血:脳内の血管が何らかの原因で破れて、脳の中(大脳、小脳、脳幹の脳実質内)に出血した状態を云います。
- 脳梗塞:脳の血管が詰まったり、何らかの原因で脳の血のめぐりが正常の5分の1から10分の1位に低下し、脳組織が酸素欠乏や栄養不足に陥り、その状態がある程度続いた結果その部位の脳組織が壊死(梗塞)してしまったものです。
- くも膜下出血-脳の表面を覆う膜の一つの「くも膜」の下に出血がある状態で、原因は脳の血管の膨らみである「脳動脈瘤」の破裂によることがほとんどです。
心臓肥大:心臓から血液を送り出す時、高血圧などによって、心筋に通常より高い負荷がかかると、その負荷に打ち勝つため心筋が厚くなり、心臓肥大を起こします。
虚血性心疾患:心臓に酸素と栄養を送る冠状動脈の障害によって、血流が減少又は不足して起きる心疾患の総称です。
- 狭心症:冠動脈の内側が部分的に細くなると、心筋への血流が悪くなって、一時的に胸の痛みを感じる状態を云います。
- 心筋梗塞:冠動脈血管に閉塞や狭窄などが起きて血流量が下がり、心筋が虚血状態になり壊死してしまった状態で、通常は急性に起こる「急性心筋梗塞(AMI)」を指し、心臓麻痺、心臓発作と呼ばれます。
動脈瘤:動脈壁が何らかの原因で弱くなり、その部分が押されて徐々に膨らみ、血管の一部がこぶ状になります。
腎不全:腎臓は左右に各々約100万個のネフロンと呼ばれる、腎小体と尿細管からなる機能単位によって構成され、尿の生成や細胞外液中の水・電解質の濃度を一定に保ちますが、この糸球体組織の機能が60%以下まで低下した状態を云います。
慢性腎臓病(CKD):慢性に経過する全ての腎臓病を指し、メタボリックシンドロームとの関係が深く、1,330万人(成人の8人に1人)以上の患者さんがいる新たな国民病と云われています。
初期には自覚症状がほとんどなく、一定レベルを超えると自然治癒することはなく、放っておけば、どんどん進行して透析療法や腎臓移植を行わなければいけない可能性があります。
高血圧予防の10ヶ条
① 減塩を心掛けよう
塩分の摂り過ぎは、血管内に水を取り込み、血管の拡張性を弱めて血圧を上げます。
② 太りすぎに注意!
肥満は心臓の負担を重くして、血圧を高めます。
③ バランスの良い食生活を!
各種栄養素を万遍なく摂ることが健康の基本です。特にカリウム、カルシウムを多く摂りましょう。
④ ストレスを溜めない
精神的なストレスが血圧を上昇させます。
⑤ 適度な運動を定期的に!
血液の循環を活発にして、血管が丈夫になりますよ。
⑥ 規則正しい日常生活を!
過労や睡眠不足は血圧を上昇させます。
⑦ アルコールはほどほどに!
多量の飲酒は血圧を上昇させ、肥満や動脈硬化の原因となります。
⑧ 禁煙の実行
たばこは血管を収縮させ、動脈硬化を促進する、「百害あって一利なし!」です。
⑨ 便秘の解消
排泄時の“りきみ”は血圧を上昇させます、お通じの良い食事を心掛けましょう。
⑩ 定期的に血圧を測定しましょう
血圧は健康のバロメーターです。日頃から自己管理に気をつけましょう。
高血圧の方には
急激な温度差には注意!
急激な寒さ(外出時や入浴時など)は血管を収縮させて、血圧を上げるので気を付けましょう!
降圧薬は医師の指示に従って!
降圧薬の服用を勝手に中止するのは危険です。
異常があった場合は、早めに医師の診断を受けましょう。

高血圧予防の3本柱
食生活で予防
① 食塩は1日男性8g未満、女性7g未満。高血圧の方は6g未満に抑えましょう。
② 緑黄色野菜や繊維の多い食物をたっぷり食べて、便秘も予防しましょう。
③ バランスの良い食事をしましょう。主食・副食・主菜・牛乳・乳製品・果物をバランスよく、また、カリウム・カルシウムも十分に摂りましょう。
④ 体重を上手にコントロールしましょう。
脂肪の多い食品は避けて、糖分の摂り過ぎも注意し、飲酒は男性日本酒1合、またはビール中瓶1本程度、女性はその半分くらいに、しましょう。
運動で予防
軽い高血圧の方は運動が効果的
高血圧などの方は医師と相談して、その指導の下、適切な運動を行いましょう。
高血圧で無くても、自分の身体を一生大事に使いたいなら、運動療法は必須です。薬要らず、これだけでも良いと思ってしまうぐらいです。
しかし、運動でよく間違えられるのは有酸素運動をすることが一番大事なのでは無いということです。
まず、高血圧の方は血管が硬くなっていたり、骨格筋量が少なくなっている女性が多く見られます。
そのため、まずは毎日の身体ストレッチ(血管のストレッチになります)が一番大事になります。
その次に週1~3回大きな筋肉の筋トレ(昔、学校でやった腕立て、腹筋、背筋、スクワットで良いです)。
高齢になると白筋(速筋)が赤筋(遅筋)に比べて著明に減少してきます。
これが原因で身体の冷えの原因になったり、他の臓器への血流を身体が優先するので血圧が上がることが凄く多いのです。
だから、筋トレをして筋肉量を多くすることが大事です。
この時に栄養が足りていない方は、別に栄養管理も必要になります。
自分は筋肉量が十分あると思われる方も、若い時に筋トレをしているヒトの方が、加齢によって生じる筋肉量の減少を抑えられます。
筋トレまでは必須だと思われます。
但し、いきなり筋トレをすると負担が強過ぎる方は、運動することにある程度慣れてから開始する様にして下さいね。
最後に有酸素運動です。ここまで出来れば凄く優秀です。
確かに有酸素運動は心肺機能を強くして、血管もキレイになりますし、生命予後を改善します(心不全がある場合は生活の質が高まります)。
具体的な目安としては、運動負荷量は少ししんどい~少し楽な程度、運動負荷量は週3~5を目指す、時間は30分以上/回です。
有酸素運動は適します
ウォーキング、自転車、水泳と云った有酸素運動が高血圧には適しています。
日常生活での目標歩数は、20~64歳男性で9,000歩、女性で8,500歩、65歳以上男性で7,000歩、女性で6,000歩です。
ウォーキングはニコニコペース
笑顔で話しながら歩くペースで十分です。強すぎる運動は逆効果になるので、最大酸素摂取量の50%を目安にウォーキングを楽しみましょう。
1回30分以上
「継続は力なり」と云い、続けることは大切ですが、体調によっては無理をするのも禁物です。
週に2回以上
週に2回以上行うことで、運動効果が継続されます。
1年以上は続けよう
続けて行わなければ、運動の効果が上がりませんよ。
休養で予防
睡眠をたっぷりとって、心地よい目覚めが健康のバロメーター
十分な睡眠が血圧を安定させます。
休養と仕事のバランスで過労防止と能率アップ
過度な肉体労働と精神的ストレスは高血圧の要因になります。
1日30分、ゆとりのある自分の時間
精神的なストレスは早めに解消して、心にゆとりを持ちましょう。
自然と触れ合って、心と身体のリフレッシュ
森林浴や野外の散策で、心も体もイキイキさせましょう。

主な食品の塩分チェック
塩分は1日男性8g未満、女性7g未満に抑え、高血圧の方は6g未満(大さじ約2/5)にしましょう。
| 食品 | 量 | 塩分 |
|---|---|---|
| 調味料 | 醤油15g(約大さじ1杯) | 2.2g |
| 味噌(普通味)20g(約大さじ1杯) | 1.2g | |
| マヨネーズ10g(約大さじ2/3) | 0.2g | |
| マーガリン10g(約大さじ2/3) | 0.1g | |
| 漬物 | 福神漬け30g(大さじ1杯) | 1.5g |
| 梅干し(中)8g(1個) | 1.8g | |
| たくあん20g(2切れ) | 0.9g | |
| 奈良漬20g(2切れ) | 0.9g | |
| わさび漬け10g(大さじ1杯) | 0.3g | |
| 加工食品 | たらこ70g(中1腹) | 3.2g |
| 塩鮭55g(1切れ) | 1g | |
| あじ干物80g(1枚) | 1.6g | |
| 即席ラーメン85g(1袋) | 4.8g | |
| ゆでうどん300g(1玉) | 0.9g | |
| ゆでそば220g(1玉) | 0.2g | |
| 海苔の佃煮25g(大さじ1杯) | 1.5g | |
| いかの塩辛10g(大さじ1杯) | 0.7g | |
| 食パン60g(1枚) | 0.8g | |
| 薩摩揚げ75g(大1枚) | 1.4g | |
| はんぺん80g(大1枚) | 1.2g | |
| 蒲鉾60g(3切れ) | 1.5g | |
| 魚肉ソーセージ50g(3切れ) | 1.1g | |
| ハム30g(薄切2枚) | 0.8g | |
| ベーコン30g(薄切3枚) | 0.6g | |
| 料理 | 握り寿司(1人分)醤油(大さじ1杯) | 2.4g+2.4g |
| 親子丼(1人分) | 3~4g | |
| かけそば(1人分) | 3~4g | |
| 味噌汁150g(1椀) | 1~2.1g | |
| すまし汁150g(1椀) | 1~1.5g |
いかがでしたか?
高血圧は脳卒中の大敵です、自分のため、家族のためを考えるなら、あなたの血管を大事にしてあげましょう。
脳卒中・脊髄損傷、再生医療に関するご質問・お問い合わせは、
こちらのメールフォームよりお願いします。
 【監修】脳梗塞・脊髄損傷クリニック 銀座院 院長 再生医療担当医師
【監修】脳梗塞・脊髄損傷クリニック 銀座院 院長 再生医療担当医師ニューロテックメディカル代表
《 Dr.貴宝院 永稔 》
大阪医科大学卒業
私たちは『神経障害は治るを当たり前にする』をビジョンとし、ニューロテック®(再生医療×リハビリ)の研究開発に取り組んできました。
リハビリテーション専門医として17年以上に渡り、脳卒中・脊髄損傷・骨関節疾患に対する専門的なリハビリテーションを提供し、また兵庫県尼崎市の「はくほう会セントラル病院」ではニューロテック外来・入院を設置し、先進リハビリテーションを提供する体制を築きました。
このブログでは、後遺症でお困りの方、脳卒中・脊髄損傷についてもっと知りたい方へ情報提供していきたいと思っています。